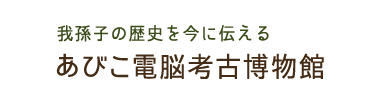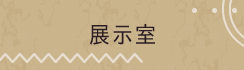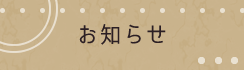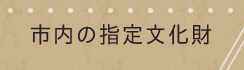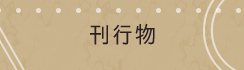旧布佐観音堂仏像(木像馬頭観音坐像1躯)
場所
延命寺(我孫子市布佐2318)
木像馬頭観音坐像

木像馬頭観音坐像
像高22.3センチメートル、三面三目八臂。頭上に馬頭面を戴き、本面は開口した忿怒相をあらわし、胸前で左右第一手は馬口印を結び、蓮華座上に右足を上にして結跏趺坐する。頭髪は炎髪で天冠台をつける。左右脇面も忿怒相をあらわすがいずれも口は閉じる。上半身には覆肩衣と衲衣をまとい、下半身に裙を着す。胸飾をつける。脇手は、右第二手は持物欠失(宝剣か)、第三手は鉞斧を執り、第四手は与願印を合わす。左第二手は持物欠失(輪宝か)、第三手は宝棒を持ち、第四手は羂索を執る。
像の構造は、頭体幹部を一材から彫出し、本面は頭上の馬頭面までを含めて彫出した別材を矧ぎ、左右脇面も別材でつくり本面の鬢髪の後ろそれぞれ矧ぐ。左右腰部に三角材を矧ぎ、膝前に一材を矧ぐ。三道下で差首とし、本面三眼に玉眼を嵌入する。脇面はいずれも彫眼。体幹後方材の背面側には襟下部から腰部に至る大きさの背面材を矧ぎつけ、同材の左右側面に穿たれた丸穴に脇手が挿入されている。体幹材の前面側底部は内刳されるが、この内刳は像を台座に固定するためのほぞ穴の役割をなしており、台座蓮肉部中央内部から一部を突出した石材がほぞの代りになっている。石材は大部分が台座内部に埋め込まれており、現状では詳細不明。像表面は後世の補修により肉身部を漆箔、それ以外を古色仕上げとする。制作年代は江戸時代中期とみられる。
解説
本像を主尊として祀ってきた布佐観音堂は『我孫子市史 民俗・文化財篇』(1990年、以下『市史』)によれば創建の時期は不明とされるが、安永4年(1775)設立の相馬霊場には第58番札所とされているため、それ以前の建立になるのはたしかであろう。現在の堂宇は昭和34年(1959)の再建であり、当初の堂は現在地よりも南東に位置していた。
江戸時代、銚子沖で採れた魚は利根川水運を利用して輸送されたが、布佐河岸でいったん陸上げされて松戸河岸までの約8kmは通し馬で陸路を運搬し、その経路は鮮魚街道と呼ばれた。そのため、布佐観音堂は鮮魚街道の運搬に貢献した数多の馬たちを供養するために街道の起点に建立され、その主尊として馬頭観音像が祀られたと考えられる。馬頭観音信仰は奈良時代には日本に流入し、中世になると六観音の一尊として普及したが、近世には六道のうち畜生道を司る菩薩として民間信仰が広がって、家畜の守護神としての性格を備えるようになり、とくに馬の供養のために石仏や石碑の造像が盛んとなった。今回(令和6年9月6日)の調査で、本像の台座内部に石が埋め込まれており、その一部が像と台座を固定するためのほぞになっているということが明らかとなったが、この石ももとは馬頭観音の石仏や馬の供養碑の一部である可能性が考えられる。
さて、当初の観音堂は明治3年(1870)の利根川決壊によって破壊されたが、堂内の仏像は回収されたという。ただし本像はこの時は出開帳に出ていたので水害を免れたとも伝えられている。大正3年(1914)ごろの利根川堤防改修工事にあわせて、前年に現在地への移転が進められて民家の建物を仮堂とした。その後地元の人々や東京魚河岸の鮮魚商の寄進により、ようやく昭和34年に現在の観音堂が建造されたのであった。本像は江戸時代のある時期から秘仏とされ、現代でも昭和48年(1973)ごろから年一回4月21日の御開帳が恒例となり、毎回多くの参詣者があったという。
観音堂は平成23年(2011)の東日本大震災で多大な被害を受け、地元住民の尽力による応急処置で凌いできたが、倒壊が懸念されるために令和6年度に解体された。そこで本像をはじめとする堂内の諸像は令和6年秋に近隣の延命寺に移坐され保管されている。
本像は江戸時代から現在まで地域の人々を中心にして篤く信仰されてきた馬頭観音である。本像は布佐を起点とした鮮魚街道と通し馬の歴史を物語る貴重な有形文化財であり、とくに観音堂が解体された今となってはその存在は非常に重要である。