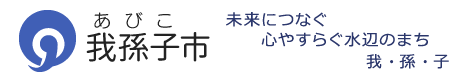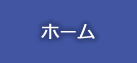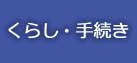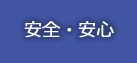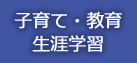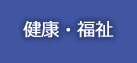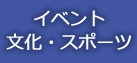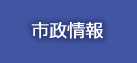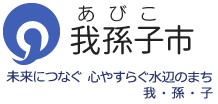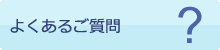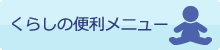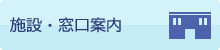保育の必要性の認定
利用に必要な「子どものための教育・保育給付支給認定」
小学校就学前の子どもが保育園・認定こども園・小規模保育事業所を利用するためには、住民登録されている市区町村による「子どものための教育・保育給付支給認定」を受ける必要があります。子ども・子育て支援法第19条に規定されている認定区分によって、利用できる施設・事業が異なります。
| 認定区分 | 年齢要件・保育の必要性の有無 | 利用できる施設など |
|---|---|---|
1号認定 |
満3歳以上で幼稚園等での教育を利用する子ども。保育の必要性なし |
認定こども園 |
2号認定 |
満3歳以上で保護者の就労等により保育の必要性あり | 保育園・認定こども園 |
3号認定 |
満3歳未満で保護者の就労等により保育の必要性あり | 保育園・認定こども園(幼保連携型)・小規模保育事業所 |
保育の必要性(2号認定・3号認定について)
1.保育の必要量
2号・3号認定を受けた場合は保育を必要とする事由により「保育の必要量」を認定します。「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の2区分に分かれます。
| 保育の必要量 | 利用できる時間 |
|---|---|
| 保育短時間認定 | 通勤時間も考慮し、8:30~16:30のうち最長8時間(園により設定時間が異なる場合あり)利用可能。延長保育は利用する必要がないこと。 |
| 保育標準時間認定 | 通勤時間等も考慮し、上記の時間を超えて最長11時間利用可能。 |
上記は最大利用時間となります。疾病等、看護等は家庭の状況によります。ご相談ください。
認定の必要量以外の保育があった場合、別途料金がかかることがあります。保育短時間、保育標準時間のどちらの認定を受けた場合であっても、保護者が実際に必要とする時間の利用となります。
保育を必要とする要件
| 事由 | 要件 | 認定期間 | 保育の必要量 | 必要書類 |
|---|---|---|---|---|
就労 |
月64時間以上の就労を常態としていること(休憩時間は含まない) | 就労証明書の記載どおり就労を継続されている期間 | 就労時間と通勤時間により認定 | 就労証明書(注釈1) |
| 妊娠・出産 | 産前産後(妊娠・出産)期間であること | 出産月の2か月前の月初から出産後2か月目を迎えた月末まで |
保育標準時間※申請により短時間認定も可 | 母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日を記入したページ)(注釈2) |
| 疾病・障害 | 保護者の病気や怪我、または精神や身体に障害があること | 療養が必要な期間 | 保育短時間 | 診断書(市所定の様式)又は障害者手帳等(注釈3)の写し(交付を受けた方のみ) |
| 介護・看護 | 同居の親族の介護や看護に常時あたっていること | 介護等が必要な期間 | 介護・看護を要する時間により認定 | (1)介護・看護状況申告書(市所定の様式) |
| 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっていること | 災害復旧に従事している期間 | 保育標準時間 | り災証明書など |
| 就学 (注釈4) | 保護者が就学または職業訓練(月64時間以上)を受けていること(休憩時間は含まない) | 卒業または修了予定まで |
授業時間等に応じて認定 | 在学証明書及びカリキュラム表 |
| 求職活動等 | 求職活動(起業準備を含む)を行っていること | 1か月間(起業準備・リストラ・倒産の場合、最長3か月間)の月末まで | 保育短時間 | 入園後1か月以内に求職活動状況報告書、認定申請書、就労証明書(1か月以内に就労を開始してください) |
| 育児休業中の在園時の継続利用 | 既に就労要件で保育認定を受けている保育者が下の子の育児休業を取得し、育児休業中も保育の継続利用が必要であると認められた場合(注釈5) | 育児休業を終了する日又は育児休業に係る子どもが3歳に達する日のいずれか早い日まで | 保育短時間 | 育児休業期間が記載された就労証明書 |
注釈1:次に該当する場合は上記に加えて下記のいずれかの書類が必要
自営業者の場合:個人事業主の開業届出書の写し、その他自営業の証明となるもの
農業従事者の場合:農地台帳
注釈2:双子以上の場合はその旨がわかるページ
注釈3:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をさします。
注釈4:学校教育法第 1 条に規定する学校、同法 124 条に規定する専修学校、同法第 134 条第 1 項に規定する各種学校、その他これらに準ずる教育施設
注釈5:育児休業中は保育認定での新規入園はできません。
| 家庭の状況 | 必要書類 |
|---|---|
ひとり親家庭の場合 |
戸籍謄本(全部事項証明書)または離婚届受理証明書 ※発行日から6か月以内のもの |
◎身体障害者手帳 |
該当する手帳の写し |
◎特別児童扶養手当の受給対象児童 |
該当する受給証明書の写し |
生活保護を受給している場合 |
生活保護受給証明書 ※証明日から6か月以内のもの |
保護者が外国籍の方 |
保護者の在留カードの写し(表と裏) |
| 転入予定の方 | (1)転入に関する誓約書 |
二世帯住宅に住まれている方 |
世帯状況申立書(二世帯住宅) |
注釈1:父母、同居の祖父母のマイナンバーがわかる書類(番号確認書類)及び申請に来た方の本人確認できる書類を保育課窓口にご持参いただければ、課税証明書の提出は原則不要です。ただし、マイナンバーによる情報連携では把握できる情報に限りがあることから、保育料決定にあたっての必要事項を確認できない場合には、課税証明書の提出を依頼することがあります。
書類について
※各書類は、状況が変更した際には再提出してください。就労先が変わったときは、前職の退職日が記載された書類も併せて提出してください。
※書類の有効期限は証明日から原則6か月間です。継続的に施設の利用を希望する場合は、少なくとも年に一度、現況届をご記入いただくとともに、上記の書類などを再度提出していただきます(現況届は利用施設を通して配布します。)。
※書式が指定されているものがありますので、ご確認ください。