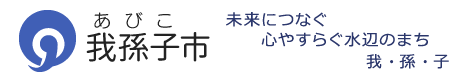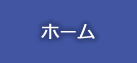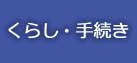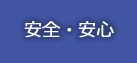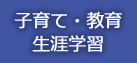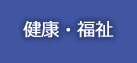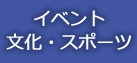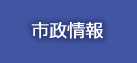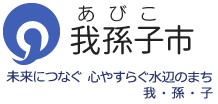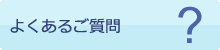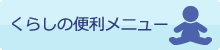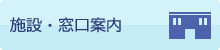建築主のみなさまへ(建物を建てた後のご案内)
建物を建てた後
- 建物や塀などの維持管理(災害に備えて)
- 建物等の定期的な健康診断(定期報告制度)
- 建築物の用途を変更して使用するとき(用途変更)
- リフォームに関すること(契約、耐震、バリアフリーなど)
 建物を除却・解体するときの手続き(別のページへ移動します)
建物を除却・解体するときの手続き(別のページへ移動します)- 建築物や街並みについて
建物を建てた後
建物や塀などの維持管理
災害に備えて、維持管理をお願いします
地震や台風の時は、劣化した建築物の屋根材、看板、塀のブロックなどが崩れたり吹き飛ばされて、通行人やご家族の生命にかかわる危害を加えることがあり、維持管理が欠かせません。
定期的に点検していただき、劣化箇所があれば早めに専門家に相談して補修工事をお願いします。
あわせて、必要であれば建物の耐震化もご検討ください。
塀の倒壊予防
塀にも建物と同じように、構造に関する基準があります。コンクリートブロック塀の一般的な耐久年数は約30年と言われています。(日本建築学会調査)日常的に点検していただき、ひび・割れ・鉄筋のさび・傾斜などの気になることがあれば建築士やブロック塀診断士などの専門家に相談し倒壊を防止しましょう。
建物と同じように、建築基準法で塀にも構造基準が定められています。
![]() ブロック塀大辞典(全国建築コンクリートブロック工業会)(外部サイト)
ブロック塀大辞典(全国建築コンクリートブロック工業会)(外部サイト)
資料を保管しましょう
建物や擁壁をつくるときには、たくさんの書類や図面などが作成されます。補修・リフォームの計画や、売買の際に必要となる場合もあるため、大切に保管してください。建物を購入する場合は、書類と資料一式を引き継ぎましょう。
- 確認済証および確認申請図書、検査済証(確認済証・検査済証の再交付はできません)
- 竣工図、工事監理報告書、工事施工状況報告書など
- 住宅性能評価書、長期優良住宅認定通知書など
なお、長期優良住宅の所有者の変更があった場合や維持管理をやめるときには届出が必要です。詳しくは、![]() 長期優良住宅の維持管理をご覧ください。
長期優良住宅の維持管理をご覧ください。
物置、車庫、コンテナを設置する場合はご注意ください
建築物に該当する場合は、建築確認申請等の手続きや構造基準等に適合させる必要があります。![]() 建築主のみなさまへ(建物を建てるときのご案内)のページを参照
建築主のみなさまへ(建物を建てるときのご案内)のページを参照
定期報告制度
建物やエレベーターにも定期的な健康診断が必要です。
不特定多数の方が利用する建築物とその建築設備、エレベーターの所有者の皆さまは、指定された建築物等について、定期的に専門技術者に調査・検査させ、その結果を我孫子市長(特定行政庁)に報告することが義務づけられています。(建築基準法第12条第1項)
![]() 定期報告制度について(一般財団法人建築防災協会)(外部サイト)
定期報告制度について(一般財団法人建築防災協会)(外部サイト)
【エレベーターの所有者・管理者の皆さまへ】戸開走行保護装置、地震完成運転装置等を設置しましょう!
エレベーターが故障し、扉が開いた状態でかごが動いた場合に起こる事故や、地震時に停止した場合に起こる閉じ込めを防止するために、建築基準法施行令が改正され、平成21年9月28日以降に着工するエレベーターについては、「戸開走行保護装置」「地震時管制運転装置」の設置が義務づけられました。
それ以前に着工したエレベーターについても、安全性の向上のために、これら装置を設置することが望ましいため、まだ設置されていないエレベーターの所有者・管理者の皆さまにおかれましては、改修工事等を検討していただきますようお願いします。
建築物の用途を変更して使用するとき(用途変更)
計画の段階でご相談ください。
事故を防止するため、建築物には用途に応じて様々な基準が設けられています。部分的にでも建物を今までの使用方法から変える際は、用途変更の確認申請手続きが必要な場合があります。(建築基準法第87条)
一例:住宅や事務所から、福祉の各ホームや店舗への変更など
- 確認申請が必要な場合は、建築基準法の適合状況の調査等が行えるように、建築士等の設計者と契約することを前提に計画を進めてください。
- 確認申請などの手続きが不要な場合においても、変更後も建築基準法に適合している必要があります。
- 用途変更後に、不特定多数の方が利用し一定規模以上となる場合は、定期報告制度の対象となります。
詳しくは、建築住宅課までお問い合わせください。
[建築基準法の適合状況の調査]
不特定多数の方が利用する建物は、火災時の延焼等を防ぐために壁で区画したり、煙を逃がすために窓等の開口部には面積や位置の規定があります。そして、ただ現場を見ただけでは、移動したりなくして良い壁や窓なのかという判断ができず、確認申請の図面や各種計算などと突き合わせて、やっと建築基準法の適合状況が判明します。
検査済証があり、その後に改装などをしていなければ、建築当時の建築基準法の規定には適合していたこととなり、現行の規定にあわせなければいけない所を、用途変更の際に改修することとなります。
検査済証がない場合には、確認申請の内容で建てられたかどうか不明のため、現況がどうなっているのかの確認作業が必要な場合があります。
参考:![]() 「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について(外部サイト)
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について(外部サイト)
リフォームに関すること
耐震リフォーム
- 木造住宅の安易な工事は、かえって耐震性が低下することがあります。耐震診断士でもある建築士等に依頼しましょう。
- 主に戸建住宅では、耐震工事以外のリフォームを耐震工事と同時に行うことで、費用を有効活用できます。屋内側から施工する方法や、外壁の改修と同時に外側から施工する方法など、住みながら耐震工事をする選択肢が広がってきています。
- 建築基準法の構造に関する規定が、昭和56年および平成12年に比較的大きく改正されています。建築基準法は最低基準のため、旧耐震基準の建物では「倒壊する可能性が高い」という耐震診断結果が出る場合もあります。我孫子市では、より優先度の高い昭和56年6月以前の基準で建てられた自己居住用の木造住宅の耐震診断と耐震改修工事について、また自己居住用のマンションの耐震診断について
 助成制度があります。該当される場合には活用をご検討ください。
助成制度があります。該当される場合には活用をご検討ください。
![]() 耐震診断・耐震改修を行うための各種情報(一般財団法人日本建築防災協会)(外部サイト)
耐震診断・耐震改修を行うための各種情報(一般財団法人日本建築防災協会)(外部サイト)
バリアフリーのリフォーム
一般的な答えはなく、個人の状況、他の家族の状況(介護方法)または予算などに応じて、きめ細かな配慮が求められます。病院等の作業療法士、建築士(福祉住環境コーディネーターなどの資格を持つ建築士)に相談し、設備機器メーカーのショールームなども活用しましょう。
リフォームの参考リンク
リフォーム業者(工事施工業者)に直接依頼する場合は、建築士が介在するか確認しておくと安心です。
工事施工者とは別に設計者(建築士)と契約すると、建築士の設計・監理料が発生する場合があります。
しかし、設計者に工事監理者として見積り査定を依頼し、複数の見積りを比較して施工者を決定するといった進め方もあります。
進め方や見積書を確認したうえで、書面により契約を交わしましょう。
![]() リフォネット(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)(外部サイト)
リフォネット(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)(外部サイト)
リフォームの進め方、トラブル防止のための事例紹介、無料相談窓口案内など
リフォーム、高齢者のお住まいのバリアフリー化、木造住宅の耐震診断・耐震改修の助成制度など
![]() リフォーム・耐震改修の税制優遇措置(国土交通省)(外部サイト)
リフォーム・耐震改修の税制優遇措置(国土交通省)(外部サイト)
税制優遇のための証明書類の発行は依頼する建築士等に直接依頼してください。
建築物や街並みについて
適正な維持管理をされた建築物や街並みは、地域の重要な財産にもなっていきます。
そうした建築物等を表彰する制度もありますのでぜひご活用ください。詳細は、千葉県建築文化賞へ
令和5年度関連行事のお知らせ
第19回住まいのまちなみコンクール 主催/一般財団法人住宅生産振興財団等 後援(予定)/国土交通省等 募集期間:令和5年5月1日(月曜日)~7月31日(月曜日)
良好なまちなみの維持管理、運営に取り組む住民組織を表彰し、受賞団体には、維持管理活動の推進のため、3年間支援が受けられます。(![]() 応募要領(外部サイト))
応募要領(外部サイト))
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ